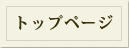
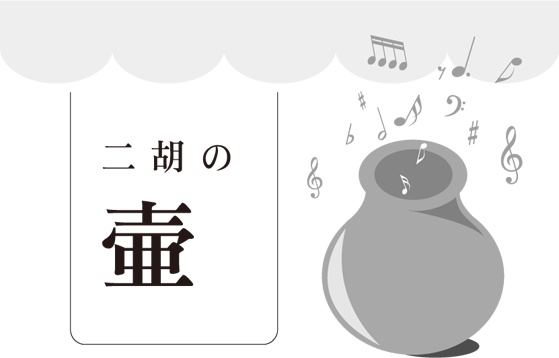
第1回・音の壷
さて、表題の「二胡の壷」、なるを教室には「カニのハサミ」、「5円玉理論」、「シナプス結合練習」などいろいろ定番のたとえ話があって、教室生はことあるごとにそれらを順繰りに聞かされる羽目になるのですが、これもその中のひとつです。
音色についての話です。二胡の勉強を始めて数年経つと、各調を一通り習い、換把(ポジション移動)やビブラートもそこそここなせるようになってくると思いますが、自分にとってさして苦労を要しない易しい曲を弾いてみたとき、音程もリズムも何がおかしいわけでもない、しかし何か物足りない、何か自分の音色に満足できないと感じる場合があります。そういう状態でモヤモヤしておられる生徒さんによく持ち出す話です。
続きは本誌をご覧下さい。
| 鳴尾牧子プロフィール | |
 |
1995年北京に留学、中央音楽学院にて二胡を学ぶ。1996年帰国後、演奏活動を開始。数少ない日本人二胡奏者として、伝統を踏まえつつ独自の感性で演奏活動を展開する。2003年より上海音楽学院教授、王永徳氏に師事。 2006年第1回中国音楽国際コンクール民族楽器部門特等賞。2010年第11回中国音楽コンクール専門の部第一位及び中華人民共和国駐大阪総領事館賞。 2008年上海之春二胡コンクールのエキシビションにて日本人演奏家として招待演奏。2010年NHK名曲リサイタル出演。 大阪、神戸で二胡の教室を主宰、積極的に後進の指導に当たる。 |