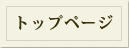
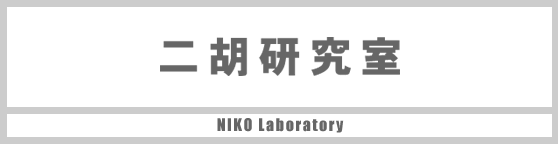

市場で紫檀と言われる木は、ローズウッド系と言えます。基本的にマメ科の木であるというのは前回にもお話ししました。紫檀と言われる理由は、木が赤いということがあげられると思います。赤と言っても、削りたては、かなり黄色に近い、オレンジ色と言ってもよい色に感じます。そして、紫檀系の全てに言えるのは、木の芯がオレンジ色で、伐採してから、次第に空気に触れて、少しづつ、紫がかった、茶色になって行くことです。その中でも、チンチャン(手違い紫檀)や、インドのローズウッドと言われる、小葉紫檀は、かなり濃いあずき色になって行きます。その他、パドウクやパーローズなどは紫がかった茶色と言えるかもしれません。
紫檀製の二胡は、出来上がってすぐは、まだ削ったばかりですから、かなりオレンジがかった色をしています。しかし木の周辺部は空気に触れると、紫に変わって行きやすく、あまりきれいには思えないものです。そのせいでしょうか、中国では二胡の仕上げに、蜜蝋にカーボンの黒い粉を入れて、全体を黒くしてしまうものが多いようです。ですから、二胡の愛好者の方たちには、何故"紫"という字がつくのか、不思議に思われる方も多いと思います。
続きは本誌をご覧下さい。